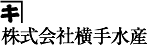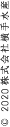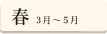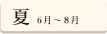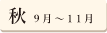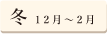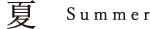太刀魚(たちうお)
・「太刀魚」の名前の由来は、見た目の形から「太刀魚」と付いたという説と、エサ(獲物)を獲る際、頭を上にして立泳ぎをすることから「立魚」と呼ばれるようになった、という説などがあります。
・一般的な魚とは異なり、背びれが頭の部分から尾にかけて途切れることなく続いていること、腹ビレや尻ビレがなく、尾ビレも背ビレの延長にひも状に伸びています。最大で230㎝を超える記録もあるようです。
・主な産地は愛媛県で、次いで大分県、和歌山県となっています。
・底引き網や定置網で多く獲れますが、体に傷が付きやすく安値となってしまいます。釣り物は傷もなく綺麗で、活け締めされたものもあり、その分高値で取引されます。
・夏から秋にかけて、釣りの対象としても人気があります。
・小骨が多い魚ですが、骨離れが良く、塩焼きやムニエル、フライ、みりん漬けの一夜干しなどにしても非常においしい魚です。
〇刺身 〇つつ切りにした塩焼き 〇バナナフライ(バナナを挟んだフライにカクテルソースがけ)

鱸(すずき)
・スズキの名前の由来は、水で“すすい”だように身が白いから、などとされています。
・ブリのように成長とともに呼び名が変わる出世魚で、地方によって呼び名は異なり、統一的な定義はないようです。一般的には、コッパ→セイゴ→フッコ→スズキでしょうか。
・日本全国に生息しており、大きな河川が流れ込む内湾やその沿岸部の磯などで獲れます。海水域はもちろん汽水域や淡水域でも生息できます。
・近年はルアーフィッシングで「シーバス」とも呼ばれ人気があります。「スズキの鰓(えら)あらい」といって、ハリにかかると大きく口を開けてジャンプし、その独特の鋭いエラで糸を切ろうと激しいファイトを見せることが、釣り人の心をとらえるようです。
・島根県宍道湖に産卵のために海からやって来る腹太スズキは『宍道湖七珍』のひとつにもなっており、「スズキの奉書焼き」はこの地方の名物料理になっています。
・スズキのあらいは、薄く刺身にしたのち、冷水で洗い、ふきんでふき上げ、梅肉かわさび醤油で食べます。その他塩焼きも独特な風味が楽しめます。
〇鱸のたで味噌焼き 〇鱸のムニエル

鯵(あじ)
・「アジ」は、スズキ目アジ科アジ亜科に含まれる魚の総称で多くの種類がありますが、日本ではその中の一種「マアジ」を指すことがほとんどです。
・日本国内にはたくさんのブランドアジがあり、 愛媛県西宇和郡伊方町の「岬あじ(はなあじ)」、 愛媛県三瓶町「奥地あじ」、 大分県佐賀関の「関あじ」、 山口県萩市「瀬付きあじ」、島根県浜田市の「どんちっちあじ」等々、場所・時期などでブランド化されています。
・一年中、魚店・スーパーなどで見かけない日はないほど一般的でありますが、全体に丸いもので、黄色いものと黒いものがあれば、黄色い方を選ぶのがポイント。また、体表の輝いているもの、鰓が鮮紅色のものが新鮮です。さらに、マアジは大きすぎるものよりも、中型がよいとされます。
・「味がよいからあじ」と言われるほどおいしい魚でご家庭で作るポピュラーな料理に使われています。
〇たたきや刺身 〇酢の物 〇塩焼き 〇唐揚 〇甘酢漬 〇南蛮漬 〇鯵のフライ 〇味噌包み揚げ 〇煮つけ

鮎(あゆ)
・独特の香りから「香魚」とも呼ばれますが、中国語では「香魚 シャンユー」が標準名とされています。
・鮎の語源は、神功皇后がアユを釣って戦いの勝敗を占ったとする説、河川の苔のついた石の周りを自分の縄張りとして独占するところからつけられた、など諸説あります。
・秋に川で産卵し海に下り、春にまた川に遡上し、縄張りを持つようになり、岩などについた苔を食べつつ黄色っぽくなってきます。自分の縄張りに侵入してきた他の鮎を体当たりして追い払う習性があり、これを利用したのが夏の風物詩ともなっている「アユの友釣り」です。
・「香魚」とも言われるほど香りのよい魚であるため、その香りを楽める塩焼きが一番です。市場に入荷するのはほとんど養殖ものですが、天然ものはあごの横下のあたりに苔を食んだ時にできるスレたような跡があります。
・魚の王様と呼ばれる鯛に対して、女王は鮎だと言われています。
〇鮎の塩焼き 〇甘露煮 〇鮎めし 〇鮎の開の一夜干し 〇一尾ずし 〇鮎の背越造り 〇子持ち鮎の有馬煮 〇落鮎の煮付け

鰯(いわし)
・源氏物語の作者紫式部がある時いわしを食べたところ非常においしく、もう一度食べたいと思っていました。ところがいわしは卑しい(いやしい)に通じると平安貴族からは嫌われていたので、夫の藤原宣孝が留守の時こっそり焼いて食べました。しかし夫宣孝がほどなく帰ってきてしまい、部屋にこもっている臭いでたちまち露見してしまいました。「こんな卑しい魚を食べるとは・・・」と叱る夫に、式部は和歌でこう返しました。「日の本に はやらせ給う いわしみず 参らぬ人は あらじとぞおもふ」 <日本で流行っている岩清水八幡宮にお参りしない人はいないように、こんなおいしい いわしを食べない人はいませんよ>これ以降、宮廷の女房言葉で鰯のことを「むらさき」と呼ぶようになった、とか。
・いわしは、「卑しい」が転訛したもの、ほかの魚にすぐ食べられてしまうので「弱し」、水から揚がるとすぐ死んでしまうので「弱い」、などから転訛したとも言われます。
・古くは「海の牧草」とまで言われるほどたくさん獲れた魚ですが、昨今は漁獲量が激減しており、鮮魚、加工品とも国産であれば決して安くはありません。 ただ、流通手段の発達から刺身でも煮ても焼いても良く、 さらに加工品はスーパーなどでは定番的なものとなっています。
・カタクチイワシを正月に使います。「田作り」と言われ、縁起物として正月には欠かせない飾です。
〇鰯の梅干し煮 〇千葉の名物なめろう 〇つみれ 〇鰯の蒲焼 〇鰯の利休漬

鰈(かれい)
・カレイには種類が多く、日本近海だけでもナメタガレイ・ババカレイ・メイタガレイ・イシガレイ・ヤナギカレイ・ムシガレイ・オヒョウなど40種以上もあります。このため地方によって呼び名、味、旬も様々です。
・漁獲量が最も多いのは北海道で、次いで島根県、兵庫県となっています。全体的には山陰から北海道にかけての日本海側で多く獲れています。
・カレイは概して長寿で40~50年生きるものもおり、このため成長が遅く、出荷サイズまでの養殖はほとんど行われていないのが現状です。
・一般に「左ヒラメに右カレイ」と見分け方が言われますが、両者ともカレイ目に属しており、腹を手前に置いて左に顔があるのがヒラメ、右にあるのがカレイとされます。ところがこれは日本のみで通用することのようで、アメリカ西海岸では左に顔のあるカレイが50%、アラスカでは70%いるとのこと。ただし、日本でも唯一「ヌマガレイ」は左向きです。
・冬の産卵前のメスは大きな卵巣をもっており、子持ちガレイと呼ばれ、甘辛く煮付けたものは日本の冬の味覚として好まれます。
・鰈は小骨が少ないので子供さんたちに食べやすい魚です。
〇煮つけ 〇姿の唐揚 〇子持ガレイの煮つけ